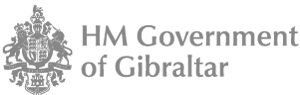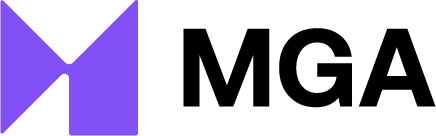프라그마틱무료 (Pragmatic Play)
iGaming 업계에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 프라그마틱 게임은 모바일 중심의 혁신적이고 표준화된 광범위한 포트폴리오를 자랑합니다. 고품질 엔터테인먼트에 대한 우리의 헌신은 비할 데 없으며, 슬롯, 라이브 카지노, 빙고 등 다양한 제품을 통해 모든 고객에게 최고의 경험을 제공하기 위해 전념하고 있습니다.
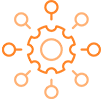
다양한 게임들을 쉽게 즐길 수 있습니다: 슬롯, 라이브 카지노, 빙고, 가상 스포츠, 스포츠 베팅을 단일 API 연동으로 접근할 수 있습니다.

20여 개 이상의 관할 지역에서 인증받은 라이센스를 보유 중입니다.
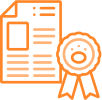
다양한 수상 경럭 콘텐츠 보유

모바일, 데스크톱, 33개 언어와 모든 화폐
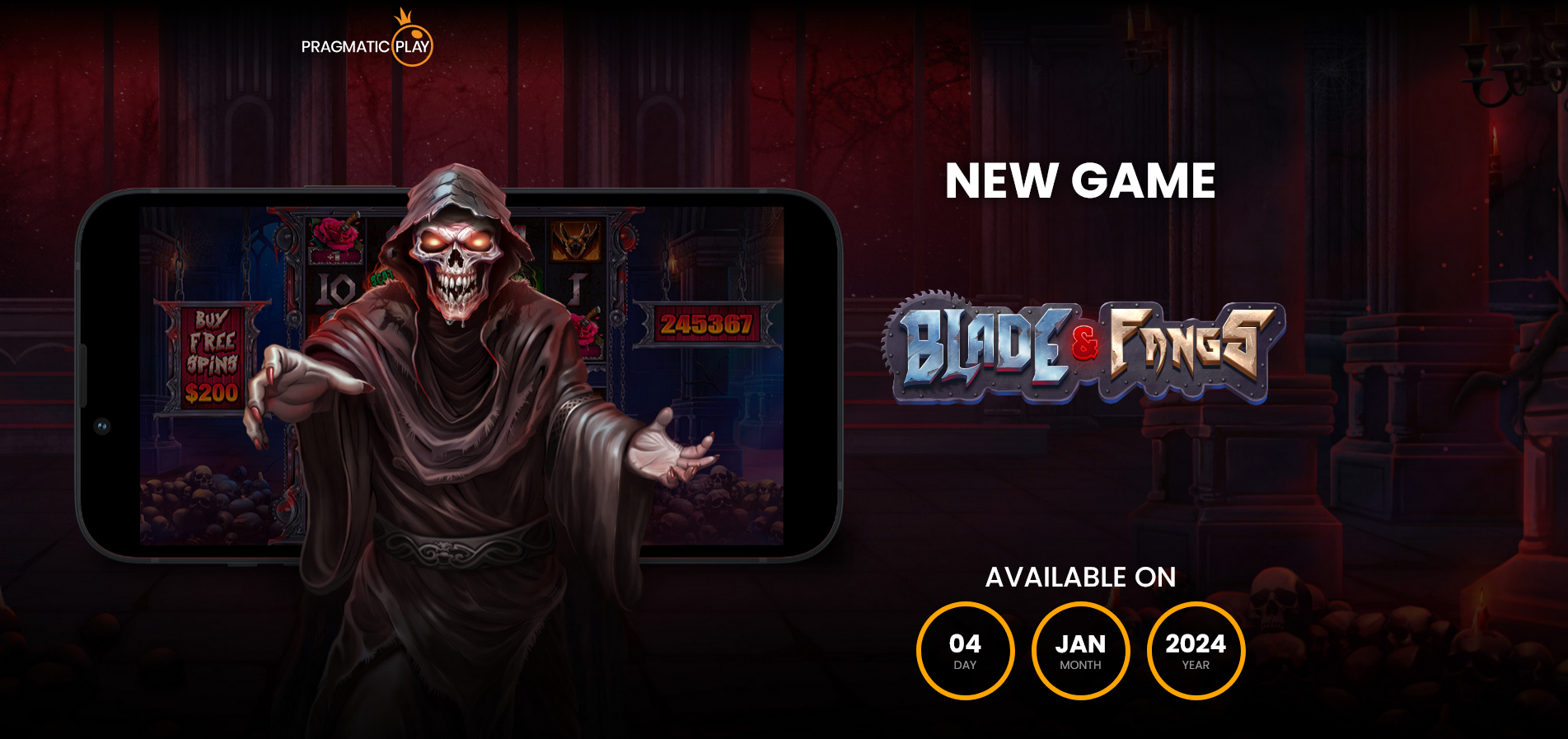
라이센싱 (Licensing)

MGA는 몰타의 게임 활동 전반을 관장하는 독립적인 단일 규제 기관의 역할을 수행하고 있습니다,
산업 내에서 효과적이고 법적인 프레임워크 및 기업 구조 보장에 중점을 두고 있습니다.

영국 내에서 상업적 게임의 허가 및 규제를 위해 설립된 도박 위원회는 독립적인 기관이며, 인가된 당국과 협력합니다. 공공 기관은 디지털 문화 미디어 스포츠 도박 위원회(DCMS)의 지원을 받아 허가 받은 자에 대한 규정을 설정하고, 이의 준수 여부를 평가합니다.

인증 (Certification)

독립적인 사설 게임 테스트 실험실인 BMM Testlabs는 1981년 11월 27일에 설립되었으며, ISO 17025 IT 및 17020 검사 기관 인증을 획득했습니다. 이 회사는 400개 이상의 관할 지역에서 인정받고 있으며, 13개국에 14개의 사무소를 운영하고 있습니다.

Gaming Associates는 독립적이고 국제적으로 공인된 ATF(Acredited Test Facility)입니다. ISO 9001, ISO/IEC 17025 및 PCI QSA 인증을 받은 회사로, 전 세계적으로 당국의 인정을 받고 있습니다.


















![프라그마틱 [엑스칼리벌 언리쉬드]](static/picture/Bingo-Thumbnail-Bingo-Blast.png)
![프라그마틱플레이 [빅 배스 스플레쉬]](static/picture/Bingo-Thumbnail-Sweet-Bonanza-Bingo.png)
![프라그마틱플레이 [스네이크 & 레더스 메가다이스]](static/picture/296x176_Diamond-dazzle.png)
![프라그마틱플레이 [쥬씨 후르츠]](static/picture/Bingo-Thumbnail-Boombox.png)
![프라그마틱플레이 [악토비어 포춘즈]](static/picture/Bingo-Thumbnail-Country-Roads.png)
![프라그마틱플레이 [스파르탄 킹]](static/picture/Bingo-Thumbnail-Release-The-Kraken.png)
![프라그마틱플레이 [북 오브 아즈텍 킹]](static/picture/Bingo-Thumbnail-Rock-N-Swing.png)
![프라그마틱플레이 [다운 더 레일즈]](static/picture/Bingo-Thumbnail-The-Jackpot-Room.png)
![프라그마틱플레이 [더 그레이트 치킨 이스케이프]](static/picture/Bingo-Thumbnail-Snowball-Blast.png)
![프라그마틱플레이 [파이어 핫 40]](static/picture/Bingo-Thumbnail-Zoom-Room.png)






![프라그마틱플레이 [좀비 카니발]](static/picture/evolution-gaming-ISO27001-certificate-EN-20231.png)